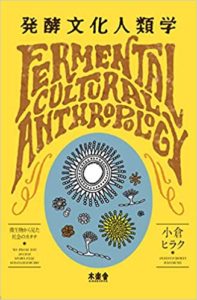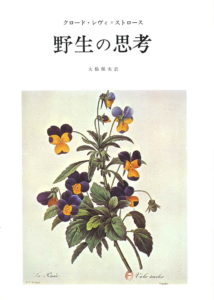2024年より国立琉球大学ウェルネス研究分野との共同研究が始まります!※【早割】は定員になり次第締め切ります!
ケアする仕事の医療人類学オンライン勉強会2024
ブルーゾーン沖縄と医療人類学:ヌアット・タイ(nuad thai)から学ぶケアの知恵
共同研究勉強会の参加者を募集します。どなたでも参加頂けます。
動画にて詳細をご紹介しています。是非ご覧ください(30分程度)
≪共同研究勉強会に参加するメリット≫
✓自分の可能性が開かれる
✓自分や周りの健康的な生き方のヒントを得る
✓居心地のよい居場所がひとつ増える
✓ハーブ食の専門家になる、というアイデア
✓ヌアット・タイの真髄に触れる(公認セラピスト・サロン)
✓大学で学び直しをする、という発想(共同研究勉強会修了証)
2024年共同研究勉強会の申込フォームはコチラ
/
過去のテーマ
\
2023年≪フレームを問い直す≫
2022年≪タイ伝統医療をめぐるケア≫
動画視聴が可能です(有料)。ご希望の場合はメールにてお問合せ下さい。
その他ご不明な点は
risho-thai@gmail.com までご連絡お願いします。
*
この勉強会は、医療人類学という学問を中心とした勉強会です。内容に興味のある方でしたらどなたでも気軽に参加いただけます。
教養のある大人になるためにもう一度学び直したい、学術的な知識に触れたい。
そういった気持ちが高まる大人が年々増えているといいます。
わたしもそのうちのひとりです。
たとえば、大学に通い直すことは色々な事情で難しいけど、今はそこまで本格的でなくても・・・でも学び直したい、といった方が、参加しやすいようなオンライン勉強会を企画します。
この勉強会は「ケア」をキーワードに進めていきます。
今、「ケア」という言葉は世の中に溢れています。
健康や美容であつかわれる手ごろな「ケア」、医療や福祉であつかわれる専門的な「ケア」、あるいは環境問題など政治・経済のあいだであつかわれる国家規模の「ケア」・・・一口にケアといっても、その概念はいろいろな意味合いで使われています。
生きていくなかで、誰しもケアを必要とするとき、あるいは誰かからケアを必要とされるときがあるものです。ケアについて考えてみることは、誰にとっても役立つ学びになるのではないでしょうか。
まずはユルユルと、皆さまと大人の学び場をつくっていければうれしく思います。
世話役 石田ミユキ・生田和代余